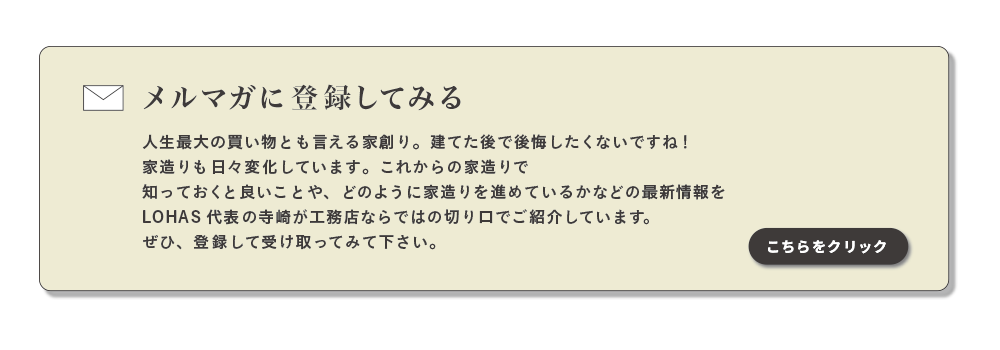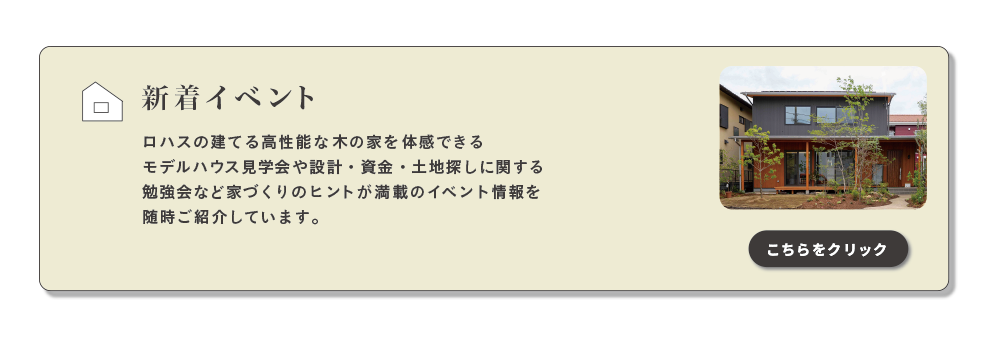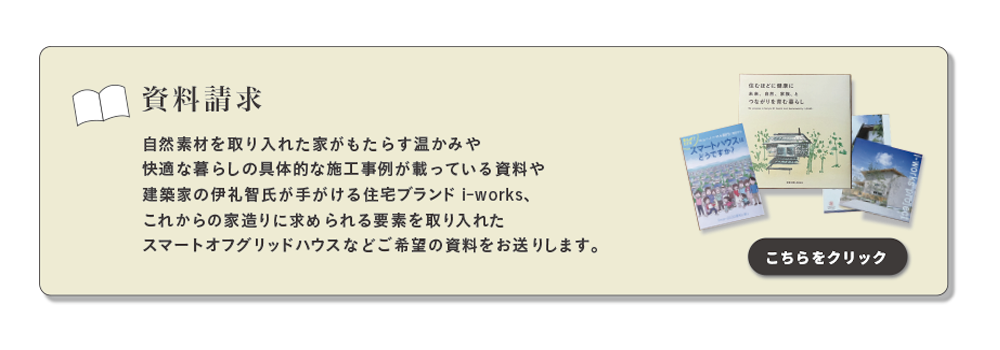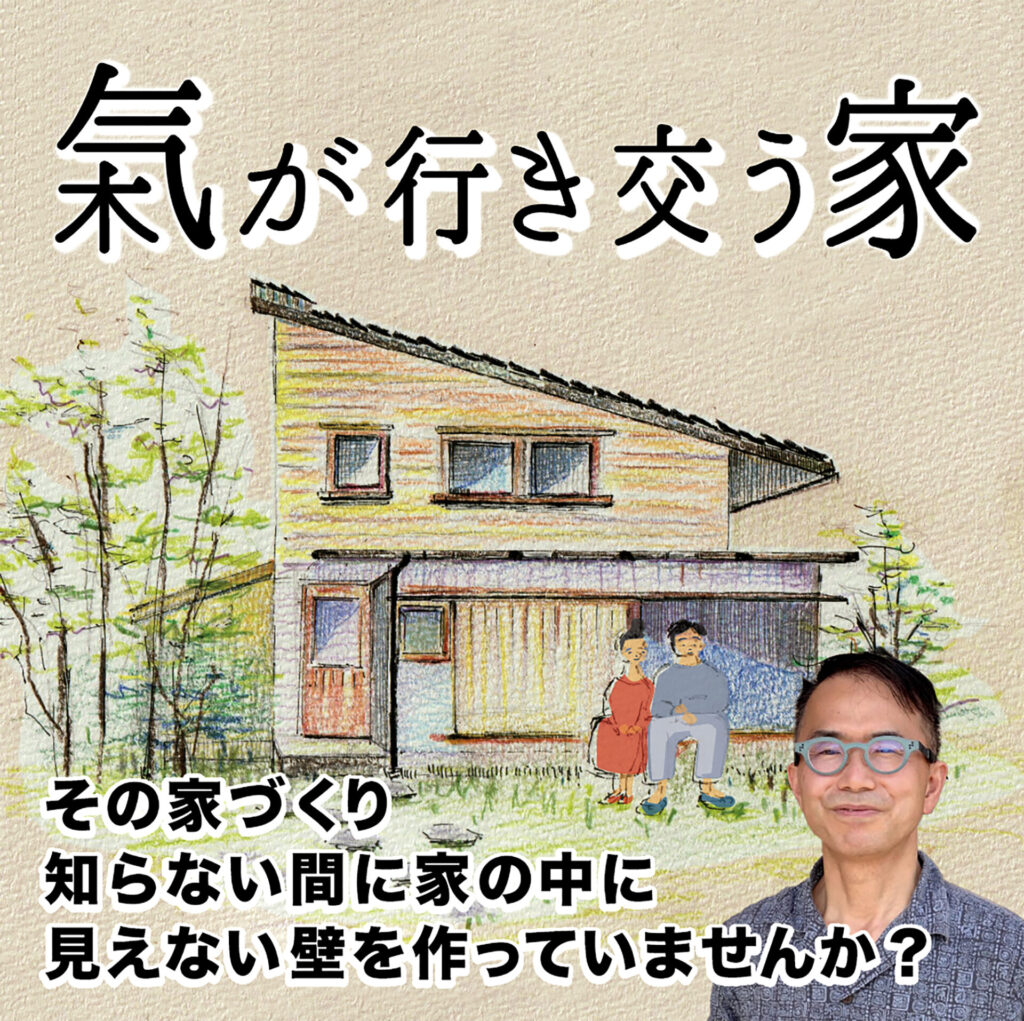近年、新築住宅を建てる際に注目されているのが「DR補助金」です。
家庭用蓄電池の導入を支援するために、国で行っている制度になります。
DR補助金を利用すると、初期費用の削減につながるなどのメリットがあります。
ただし「DR補助金を活用して後悔しないか」と不安になる人もいるのではないでしょうか。
DR補助金はデメリットを把握し、早めに対策を取ることが重要です。
今回はDR補助金の基本的な仕組みやデメリット、注意点を分かりやすくご紹介します。
DR補助金を活用して住まいを建てたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事でわかること
- 知っておきたいDR補助金のデメリット
- DR補助金を利用することで得られるメリット
- DR補助金を利用する際の3つの注意点
DR補助金の基本的な仕組み

DR補助金は、家庭用蓄電池の導入を支援する国の制度です。
再生可能エネルギーの活用や、電力の安定供給を目的としています。
まずは、DR補助金の仕組みや対象となる機器、補助金額の目安など、基本的な情報をご紹介します。
DR補助金制度の概要
DR補助金とは、家庭におけるエネルギー使用量を効率的にコントロールすることを目的にした国の支援制度です。
DRとは「デマンド・レスポンス」の略称で、電力の需給バランスが逼迫した際に電力会社から節電を呼びかけられ、それに応じて家庭側が使用電力を抑える仕組みです。
DR補助金はこうした節電の仕組みに参加する家庭に向けて、太陽光発電や家庭用蓄電池などの導入費用を一部支援してくれます。
今後、再生可能エネルギーの活用や脱炭素社会の推進が求められる中で、注目を集めている制度です。
DR補助金の対象要件
DR補助金を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず前提として、DRに対応する家庭用蓄電池を導入することが求められます。
対象となる機器のスペックやメーカーが決まっていることも多く、自由にどんな製品でも選べるわけではありません。
さらに、電力会社やサービス事業者と連携し、節電要請に対応する契約を結ぶ必要もあります。
申請のタイミングや工事着手の日程、事業者登録制度に則った手続きなど、細かな要件を確認しながら進めましょう。
DR補助金は制度の変更もあるため、常に最新情報を確認しつつ住宅会社や専門業者と連携して申請準備を進めることが重要です。
DR補助金の補助金額
2025年度のDR補助金制度の補助金額は、1申請当たり60万円が上限です。
V2Hなどと併用するケースやHEMSとの連携など、高度なエネルギー制御を実現できる場合には加算が適用されます。
ただし、申請のタイミングや条件を満たしていないと、補助金が受け取れない可能性があります。
事前に必要な書類や条件を確認し、設計段階から補助金活用を見据えた住宅計画を立てることが大切です。
参照:一般社団法人 環境共創イニシアチブ「DR家庭用蓄電池事業」
DRに対応した機器
DR補助金を活用するには、DRに対応した機器の導入が必要です。
中心となるのは、家庭用蓄電池とそれに接続するHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)です。
DRに対応した機器は電力会社からの節電要請に応じて、自動的に蓄電池からの放電や家電の制御をします。
国が定めた要件があり、登録された製品でなければ補助金の対象になりません。
DRに対応した機器が、自分たちのライフスタイルに適しているかをしっかり検討することがポイントです。
DRが注目されている理由
DRが注目されている理由のひとつは、電力の需給バランスが年々不安定になってきていることが挙げられます。
猛暑や寒波による電力需要の急増、災害による電力供給の停止など、私たちの暮らしはさまざまなリスクにさらされています。
そうした中で、家庭のエネルギー使用を柔軟に調整できる仕組みとして、DRが注目され始めました。
さらに、カーボンニュートラルの実現に向けて、電力の安定供給と環境負荷の軽減を両立できる手段としてもDRはますます重要な存在になっていくと考えられています。
参照:一般社団法人 環境共創イニシアチブ「DR家庭用蓄電池事業」
知っておきたいDR補助金のデメリット

DR補助金は家計の負担を軽減し、省エネにも貢献できる魅力的な制度です。
ただし、利用にあたってはいくつかの注意点も存在します。
ここからは、DR補助金のデメリットについて解説します。
1.申請手続きが複雑である
DR補助金を活用するには、さまざまな書類の提出や条件の確認が必要です。
具体的には、機器のスペックや設置計画を記載した申請書や設置完了後の実績報告や証明書類の提出も求められます。
申請は工事着手前に行う必要があるため、手順を誤ると補助が受けられなくなる可能性も。
自治体の補助金と併用する場合は求められる書類や申請時期が異なり、より慎重な対応が大切です。
蓄電池導入を家づくりと並行して進めるには、情報収集や準備の時間を十分に確保しておきましょう。
2.電力の需要過多で蓄電池を遠隔操作される場合がある
DR補助金は電力の需要が高まり供給が逼迫する際に、電力会社やサービス事業者からの要請により蓄電池の充放電を遠隔で操作する場合があります。
ピーク時には蓄電池の放電を促されることで、家庭の電力使用が制限されるケースもあります。
安全性や利便性は考慮されていますが、「電力を自分で管理したい」「災害時に備えて満充電を維持したい」と考える方は、不自由さを感じることがあるかもしれません。
ライフスタイルや災害時の備えを重視したい方は、DRの仕組みが自分の家庭に合っているかどうかを事前に確認しておきましょう。
3.設置機器の選択肢が限られるケースがある
DR補助金の対象機器は国や事業者が定めた一定の要件があり、どんな製品でも自由に選べるわけではありません。
とくに家庭用蓄電池は、DR対応機能や通信機能を備えた特定の機種に限定されている場合が多く、「デザイン性」「価格」「メーカーの信頼性」などユーザーが重視したい要素と合わないこともあります。
補助金を優先するあまり、必要以上に高性能な機器を導入してしまう場合もあります。
家づくりにおいては、住宅全体の設備バランスや将来のメンテナンス性も重要なポイントです。
DR補助金を利用することで選択肢が狭まりすぎてしまわないように注意し、納得のいく機器を選びましょう。
DR補助金を利用することで得られるメリット

DR補助金を活用するとデメリットがありますが、多くのメリットもあります。
ここでは、DR補助金を利用することで得られる代表的なメリットについて、詳しくご紹介します。
1.初期費用を抑えられる
DR補助金は、初期費用を抑えられるのが大きなメリットです。
家庭用蓄電池は高性能である一方、導入には数十万円から数百万円の費用がかかります。
高額な初期費用が蓄電池導入のハードルとなっている方にとって、DR補助金は心強い制度です。
補助金を活用すれば、機器の購入費や設置費の一部が支援され、自己負担額を大幅に減らせるでしょう。
自治体によっては独自の補助制度と併用できるケースもあるため、さらにコストを削減できる可能性があります。
2.家庭用蓄電池が災害時に備えられる
家庭用蓄電池は、災害時に備えられるのもメリットです。
蓄電池は地震や台風などの自然災害による停電時に、非常用電源として活躍します。
太陽光発電と連携すれば昼間に発電した電気を蓄えておき、照明や冷蔵庫、スマートフォンの充電など最低限の生活機能を維持することが可能です。
DR補助金を活用して蓄電池を導入しておけば、いざというときにライフラインを確保できるでしょう。
3.環境に貢献できる
家庭用蓄電池を活用すると、環境に貢献できるのもメリットです。
日中に太陽光発電で得た電気を蓄え、電力需要の高い時間帯に使用すると火力発電に頼らない生活が実現します。
DR補助金を通じて電力消費を調整することは、社会全体の電力需給のバランスを取る取り組みに貢献できます。
DR補助金を利用することで、エネルギーの自立と地球環境の保護のどちらにも寄与できるでしょう。
4.太陽光発電と家庭用蓄電池を組み合わせて売電収入を得られる
太陽光発電と家庭用蓄電池を組み合わせれば、売電による収入を得られるのもメリット。
昼間に使いきれなかった電力を蓄電池に貯めておき、必要に応じて利用することで電力会社から買う電気を減らせます。
さらに、余剰電力を電力会社に売れば、収入源になります。
DR補助金を活用すると、日々の家計にもプラスに働くでしょう。
自然素材の家とは?メリット・デメリットや失敗しないポイントを解説
家庭用蓄電池のメリットデメリット|太陽光発電との相性やスマートハウスについても解説【静岡県富士市の施工事例付き】
DR補助金を利用する際の3つの注意点

DR補助金は家庭用蓄電池の導入を後押ししてくれる心強い制度です。
ただし、申請や活用にはいくつか注意すべきポイントがあります。
ここからは、DR補助金をスムーズに活用するために押さえておきたい3つの注意点をご紹介します。
1. 家庭用蓄電池が自分たちのライフスタイルに合っているかを確認する
家庭用蓄電池は、自分たちのライフスタイルに合っているかを確認することが大切です。
日中に家に誰もいない家庭では、太陽光発電による電気を蓄えるメリットが活かしにくくなります。
災害時の備えとしては心強いですが、普段の電力使用量が少ない家庭では導入効果につながらないこともあります。
蓄電池を導入する際はライフスタイルや電気使用パターンを把握し、費用対効果を見極めましょう。
2.他の補助金と併用できるか調べる必要がある
DR補助金を利用する際は、他の補助金と併用できるかを調べる必要があります。
国や自治体には、さまざまな補助制度が用意されています。
制度によっては、併用が制限される場合もあるでしょう。
自治体独自の補助金は申請期間や予算が限られていることもあるため、早めに情報収集をしておくことが重要です。
3.家庭用蓄電池を導入する際は実績豊富な施工会社に依頼する
家庭用蓄電池を導入するには、実績豊富な施工会社に依頼しましょう。
蓄電池を設置するには電気工事なども必要になるため、施工の品質が安全性に直結します。
施工実績の豊富な会社を選ぶことで、安心して蓄電池を利用できるでしょう。
DR補助金を申請する際も、スムーズに申請できます。
安心して任せられる施工会社に依頼することで、補助金のメリットを最大限に活かせるでしょう。
空間工房LOHASは、家庭用蓄電池を導入した省エネ住宅の施工実績が豊富です。
DR補助金について詳しく知りたい方は、空間工房LOHASにお気軽にご相談ください。
まとめ|DR補助金のデメリットを理解して後悔をしない家づくりをしましょう

DR補助金は家庭用蓄電池の導入を検討している方にとって、大きな後押しとなる制度です。
初期費用を抑えつつ、エネルギーの自給自足や電気代の節約、災害時の備えなど、安心で快適な住まいづくりができます。
一方で、補助金の申請には条件や期限があり、導入後にはDR対応への理解と協力も必要です。
DR補助金を利用するメリットとデメリットをしっかりと理解し、自分たちのライフスタイルに合っているかを見極めることが大切です。
後悔のない家づくりのためにもDR補助金を賢く活用して、快適で持続可能な暮らしを実現しましょう。
空間工房LOHASは、家庭用蓄電池を導入した省エネ住宅の施工実績が豊富です。
DR補助金について詳しく知りたい方は、空間工房LOHASにお気軽にご相談ください。